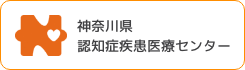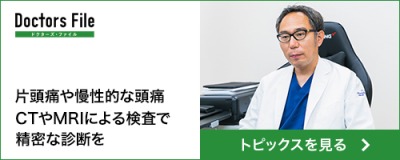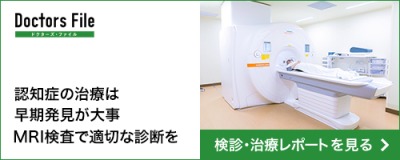2025/06/12
この記事を書いた人

えびな脳神経クリニック
院長 岩田智則
日本脳卒中学会(評議員)
日本血管内治療学会(評議員)
日本脳循環代謝学会(評議員)
米国心臓協会国際フェロー(Fellow of AHA・脳卒中部門)
日本神経学会専門医/指導医
日本内科学会総合内科専門医/指導医
日本脳卒中学会専門医指導医
日本認知症学会専門医指導医
厚生労働省認定外国人医師臨床修練指導医

脳の病気は突然発症し、患者さんやご家族の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。
海老名市にあるえびな脳神経クリニックでは、病気を「点」ではなく「線」で支える医療を実現し、脳の疾患でお困りの方をゼロにすることを目指し、日々診療にあたっています。
本ブログでは、院長の岩田 智則と理事長の尾崎 聡が、脳の健康を守るための情報をわかりやすくお伝えしてまいります。
今回は「頭痛の種類と対処法」についてくわしく解説します。
頭痛は日常的に多くの方が悩まされる症状ですが、その原因や種類によって適切な対処法が異なります。
一次性頭痛や二次性頭痛の違い、生活習慣の改善による予防法についてもご紹介しますので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
目次
頭痛の種類、その原因と対処法
慢性的な頭痛の多くは一次性頭痛に分類されますが、まれに二次性頭痛が隠れていることもあります。
そのため、頭痛の種類を正確に診断し、適切な対処をおこなうことが重要です。
特に「いつもと違う痛み」や「突然の激しい痛み」がある場合には、早急に医療機関で検査を受けることをおすすめします。
一次性頭痛
一次性頭痛は、特定の疾患が原因ではなく、繰り返し発生する頭痛です。
主に以下の3つのタイプがあります。
片頭痛
片頭痛は、ズキンズキンと脈打つような拍動性の痛みが特徴で、視野が狭くなるなどの前兆を伴うことがあります。
痛みが数時間から数日続くこともあり、日常生活に支障をきたすことが少なくありません。
片頭痛の種類
| 前兆のある片頭痛 | 痛みが始まる前に、視覚異常(閃輝暗点)、感覚異常(手足のしびれ)、言葉が出にくくなるなどの前兆が現れる。 |
| 前兆のない片頭痛(一般型片頭痛) | いきなりズキンズキンとした痛みが起こり、吐き気や光・音に敏感になることがある。 |
片頭痛が起こるメカニズム
片頭痛発作発生のメカニズムとして、現在広く受け入れられているのが「三叉神経血管説」です。
なんらかの刺激によって、硬膜血管周囲に分布する三叉神経終末からカルシトニン遺伝子関連ペプチド(CGRP)やサブスタンスPなどの神経ペプチドが放出されると、主に硬膜などの血管周辺で血管拡張、血漿蛋白の漏出、肥満細胞の脱顆粒、すなわち神経原性炎症が発生します。
神経原性炎症は三叉神経を刺激し、神経興奮が中枢へ伝達されると、大脳皮質で疼痛を自覚します。
片頭痛を誘因するもの
- ストレス疲れ
- 睡眠の過不足
- 月経周期
- 天候の変化
- 温度差
- におい
- 音
- 光
- 運動
- 欠食
- 性的活動
- 旅行
- 空腹
- 脱水
- アルコール
- 特定の食品(チョコレート、チーズ、ワインなど)
片頭痛の対処法
片頭痛の治療は、急性期治療(頓挫療法)、予防療法の2種類があります。
急性期治療(頓挫療法)
急性期治療(頓挫療法)は、頭痛発作がおこった時になるべくはやく頭痛を鎮めるための治療です。
予防療法
予防療法は、頭痛発作を起こりにくくし、発作が起こった場合でも軽く済むようにしたり、急性期治療薬が効きやすくなるようにしたりするための治療です。
これらの治療法は、片頭痛発作の回数(頻度)や程度、生活への悪影響などを基準に選択します。
緊張型頭痛
緊張型頭痛は、頭を締め付けられるような鈍痛(非拍動性頭痛)が続くのが特徴で、肩や首の筋肉の緊張、ストレス、姿勢の悪さが主な原因です。
デスクワークの多い現代社会では、特に発症しやすいタイプの頭痛です。日本人で最も多い頭痛の一つ であり、特に 長時間のスマホ・PC作業 も誘因になると考えられています。
緊張型頭痛の原因
緊張型頭痛の発症メカニズムはまだ解明されていませんが,反復性緊張型頭痛は末梢性感作(peripheral sensitization),慢性緊張型頭痛は中枢性感作(central sensitization)による疼痛メカニズムの異常が考えられています。
緊張型頭痛の誘因
・長時間の同じ姿勢(デスクワーク、スマホ使用)、ストレス、眼精疲労、運動不足、肥満、喫煙
緊張型頭痛の対処法
頻度が少なく、かつ日常生活に支障がない場合には治療は必要ありませんが、頭痛によって日常生活が制限される場合や、頻度・重症度が増している場合には治療が必要です。
反復性緊張型頭痛には鎮痛薬が有効です。鎮痛薬の使用が月に数回程度の方は通常、毎日服用する予防薬の必要はありません。
頻度の多い反復性緊張型頭痛や、慢性緊張型頭痛では抗うつ薬などの予防薬の内服、ストレスマネジメント、リラクセーション、理学療法などが推奨されています。頭痛体操なども効果的です。
群発性頭痛
群発性頭痛は、目の奥がえぐられるような激しい痛みが特徴で、20〜30代の男性に多く見られます。
数週間から数カ月の間、毎日同じ時間帯に起こるのが特徴です。
片頭痛や緊張型頭痛と並び、「3大慢性頭痛」のひとつ であり、季節性(春・秋)に発症しやすいことが知られています。
群発性頭痛の原因
発病のメカニズムは明確にされていないが,現在は4つの説が有力となっている。
- 視床下部がトリガーとなる説
- 神経ペプチドなどの変化による説
- 内頸動脈の周囲に起源を求める説
- 三叉神経の過剰興奮が副交感神経の活性化を起こすとする説
群発性頭痛の誘因
- アルコール飲料
- ヒスタミン
- ニトログリセリン
- 喫煙
群発期の飲酒は発作を引き起こしやすいため禁酒をしましょう。
また、喫煙は発症のリスク因子となる可能性が指摘されていますので禁煙も心がけましょう。
群発性頭痛の随伴症状
- 目の充血、涙が出る
- 鼻づまり、鼻水が出る
- まぶたの腫れ、瞳孔の縮小(ホルネル症候群)
群発性頭痛の対処法
急性期治療として スマトリプタンの皮下注射(保険適用)、酸素吸入(マスクで純酸素7~10L/分、15分間) が有効です。
群発期の予防療法としては 高用量のベラパミル(わが国では適用外使用が認められている) が国際的な標準薬として用いられます。
二次性頭痛(命に関わる可能性のある頭痛)
二次性頭痛は、脳や全身の病気が原因で発生する頭痛で、放置すると命に関わる可能性があります。
特に 「いつもと違う頭痛」「突然の激しい痛み」「徐々に悪化する頭痛」 は注意が必要です。
次のような場合は、早急に医療機関を受診してください。
頭部外傷による頭痛
軽症頭部外傷やスポーツ頭部外傷後に頭痛が続く場合、硬膜下血腫や脳挫傷の可能性があります。
むち打ち(頸椎捻挫) による頭痛のこともあるため、頸部の検査も必要です。
くも膜下出血
突然の強い頭痛(雷鳴頭痛)が特徴で、意識障害や嘔吐を伴うことがあります。
頭痛が突然発生し、「今までに経験したことのない痛み」と表現されることが多くあります。
脳出血
頭痛が急に出現し、手足のしびれやろれつが回らないなどの症状を伴う場合は危険です。
脳腫瘍
朝起きた時に頭痛が強く、日中は軽減する特徴があります。
頭痛とともに、視力の低下や手足の麻痺、記憶障害を伴う場合があります。
椎骨動脈解離
首の後ろから後頭部にかけての突然の激痛が特徴で、めまいやふらつきを伴うことがあります。
若年者でも発症し、マッサージやスポーツでの首の動きが原因になることがあります。
感染症による頭痛
脳炎や髄膜炎、副鼻腔炎が原因となることがあります。
意識不明や高熱、首のこわばりを伴う場合は、早急な診察が必要です。
一次性頭痛と二次性頭痛の鑑別
慢性的な頭痛は、ほとんどが一次性頭痛(片頭痛・緊張型頭痛・群発性頭痛) ですが、二次性頭痛の可能性も否定できません。
そのため、MRIやCTなどの画像検査をおこない、重大な疾患が隠れていないかを確認することが重要です。
特に次のような場合は、二次性頭痛の可能性があるため早めに医療機関を受診しましょう。
- 発熱 を伴うなどの全身症状がある頭痛
- がんの既往や免疫不全状態がある方にみられる頭痛
- 神経脱落症状や意識レベルの低下を伴う頭痛
- 突然・激烈に発症する頭痛(雷鳴頭痛など)
- 50歳以降に初めて起こった頭痛
- 頭痛のパターンが変化した、あるいは最近発症した新しい頭痛
- 姿勢によって変化する頭痛(起立性など)
- くしゃみ・咳・運動などで誘発される頭痛
- 痛みが進行する、あるいは非典型的な特徴を持つ頭痛
- 妊娠中や産後に生じた頭痛
- 眼の痛みや自律神経症状を伴う頭痛
- 外傷後に発症した頭痛
- HIVなどの免疫異常疾患を有する患者の頭痛
- 鎮痛薬の過剰使用や新しい薬剤に伴う頭痛
- 乳頭浮腫が確認された頭痛
えびな脳神経クリニックでは、MRI・CT・超音波診断装置を駆使し、二次性頭痛の可能性を除外するための精密検査をおこなっています。
頭痛の原因を的確に診断し、最適な治療をご提供いたしますので、気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
生活習慣の改善で軽減できる慢性頭痛(一次性頭痛)
慢性頭痛の多くは、生活習慣を見直すことで症状の軽減や予防が可能です。
特にストレス管理・運動・食事・睡眠の質を向上させることで、頭痛の発生頻度を減らせる場合があります。日常生活で実践できるポイントを紹介します。
ただし、生活習慣を改善しても頭痛が続く場合や、いつもと違う頭痛がある場合は、二次性頭痛の可能性もあるため、医療機関での検査をおすすめします。
ストレスを適切にコントロールする
ストレスは慢性頭痛の大きな誘因の一つです。
過度なストレスがかかると、自律神経のバランスが崩れ、筋肉の緊張や血管の収縮が起こり、頭痛を引き起こしやすくなります。
ストレスをうまく管理し、リラックスできる時間を意識的に作りましょう。
ストレスを軽減するための方法
- 適度な休息を取る(長時間の作業を避ける)
- 趣味やリラックスできる活動を取り入れる(読書・音楽・アロマなど)
- 軽い運動をする(ウォーキングやストレッチが有効)
- 深呼吸や瞑想を習慣化する
特に緊張型頭痛の方は、ストレスを溜め込まないことが大切です。
適度な運動で血流を改善する
運動不足は、血行不良を招き、筋肉の緊張や脳への酸素供給不足を引き起こします。
特にデスクワークが多い方は、肩こりや首のコリが悪化し、頭痛を引き起こしやすくなります。
軽い運動を習慣化し、血流を良くすることが重要です。
おすすめの運動
- ウォーキング(1日20分でも効果あり)
- ストレッチやヨガ(肩や首の筋肉をほぐす)
- 軽い筋トレ(筋力がつくと血流が改善される)
※ 運動のしすぎは逆効果になることもあるので、無理のない範囲でおこないましょう。
バランスの良い食事で頭痛を予防する
食生活が乱れると、血糖値の急激な変動や栄養不足が原因で頭痛を引き起こすことがあります。
特に片頭痛の方は、空腹時間が長くなると発作のリスクが高まるため、規則正しい食事が重要です。
頭痛予防のために気をつけること
- 朝食をしっかり摂る(低血糖を防ぐ)
- カフェインの摂取量を調整する(取りすぎると頭痛を誘発)
- 水分をしっかり補給する(脱水症状も頭痛の原因に)
- 片頭痛を誘発する食べ物を避ける(チョコレート・赤ワイン・チーズなど)
頭痛が起こりやすい方は、自分に合わない食品を把握し、食事を見直してみましょう。
睡眠の質を向上させる
睡眠不足や寝すぎは、頭痛を悪化させる大きな要因です。
特に片頭痛の方は、睡眠時間が乱れると発作が起こりやすくなるため、規則正しい生活を心がけましょう。
質の良い睡眠をとるために
- 毎日同じ時間に寝る・起きる(生活リズムを整える)
- 寝る前にスマホやPCを見ない(ブルーライトは睡眠の質を低下させる)
- 枕や寝具を見直す(首や肩に負担がかからないものを選ぶ)
- 寝る前にリラックスする習慣を持つ(ストレッチ・読書・ぬるめのお風呂など)
寝すぎも頭痛を引き起こすことがあるため、適切な睡眠時間(6~8時間)を意識することが大切です。
えびな脳神経クリニックでは、MRI・CTなどの画像診断を活用し、頭痛の正確な診断と治療をおこなっています。
気になる症状がある方は、お気軽にご相談ください。
原因の特定と、適切な治療の重要性
頭痛は放置せずに、まずは原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。
慢性頭痛と言われている一次性頭痛は、適切な対処をおこなうことで症状を軽減できる場合が多くあります。
また、二次性頭痛と言われている重篤な疾患でも早期に診断・治療をおこなうことで、回復の可能性を高めたり、後遺症を最小限に抑えたりすることができます。
医療機関の受診が必要な主な症状
特に次のような症状がある場合は、医療機関の受診が必要です。
- 発熱や体のだるさを伴う頭痛
- がんの既往がある、または免疫力が低下している状態での頭痛
- 手足のしびれ・脱力・意識障害などを伴う頭痛
- 突然ズキンとくるような激しい頭痛
- 50歳を過ぎてから初めて経験した頭痛
- 頭痛の頻度や痛みの強さが徐々に悪化している
- 起き上がると痛くなるなど、姿勢によって変わる頭痛
- 咳・くしゃみ・運動などで引き起こされる頭痛
- 妊娠中や出産後に始まった頭痛
- 目の奥が痛く、自律神経症状(涙・鼻水・まぶたの腫れなど)を伴う頭痛
- 転倒や事故の後に現れた頭痛
- 持病でHIVなどがある方に起こる頭痛
- 鎮痛薬を頻繁に使用しているうちに現れた頭痛
- 目の奥が腫れぼったい、見えづらいなどの症状を伴う頭痛
えびな脳神経クリニックでは、患者さんお一人ひとりに寄り添い、頭痛の原因を正確に特定し、迅速かつ的確な診断・治療をご提供しています。
気になる症状でお困りの際は、まずはお気軽に当クリニックまでご相談ください。