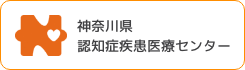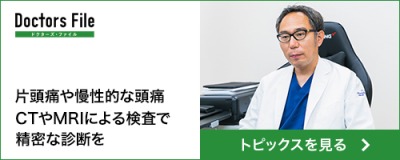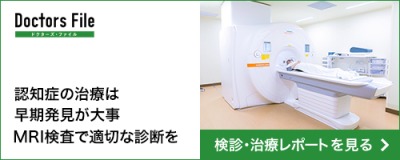2025/07/22
この記事を書いた人

医療法人社団NALU
理事長 尾﨑 聡
日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医
日本脳卒中学会 脳卒中専門医
認知症サポート医
医学博士

脳の病気は突然発症し、患者さんやご家族の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。
海老名市にあるえびな脳神経クリニックでは、病気を「点」ではなく「線」で支える医療を実現し、脳の疾患でお困りの方をゼロにすることを目指し、日々診療にあたっています。
本ブログでは、院長の岩田 智則と理事長の尾崎 聡が、脳の健康を守るための情報をわかりやすくお伝えしてまいります。
頭痛の種類と対処法については前回ご紹介しましたが、今回はその中でも女性に多くみられる「月経関連片頭痛(MRM)」に焦点をあてて解説します。
生理の前後に強い頭痛が起こる背景には、女性ホルモンであるエストロゲンの変動が関わっていることが近年の研究で明らかになってきました。
本記事では、片頭痛とホルモンの関係性、そして最新の知見を踏まえた治療や予防のヒントをご紹介します。
月経関連片頭痛(MRM)とは?
片頭痛は女性に多くみられる症状で、特に生理の前後に発作が起こりやすい「月経関連片頭痛(MRM)」は、女性特有の片頭痛タイプのひとつとされています。
一般的に月経関連片頭痛(MRM)は痛みが強く、長引きやすいため、日常生活に支障をきたしやすく、治療が難しいと感じている方も少なくありません。
このタイプの片頭痛の背景には、女性ホルモン(特にエストロゲン)の急激な変動があると考えられています。
診断には“月経との関係性”を記録することが大切
国際頭痛分類では、「月経関連片頭痛(MRM)」は月経の開始2日前から3日目までの期間に発症する前兆のない片頭痛が、3回の月経周期のうち少なくとも2回以上に出現することが診断基準とされています。
また、発作が月経の時期にしか起こらない「純粋月経時片頭痛」と、月経以外の時期にも発作が起こる「月経関連片頭痛」に分類される点も特徴です。
このため、日頃から頭痛と月経周期を一緒に記録しておくことが、適切な診断と治療の第一歩になります。
片頭痛とホルモンの関係とは?
脳内で片頭痛が起こる仕組みのひとつに、「三叉神経血管系」の関与があります。
片頭痛発作時にはこの神経が活性化され、「CGRP(カルシトニン遺伝子関連ペプチド)」という物質が放出され、脳の血管が拡張し、炎症や痛みが引き起こされます。
このCGRPの放出とホルモン(エストロゲン)の変動の関係について、近年の研究により、新たな手がかりが得られています。
最新研究が明らかにしたMRMの特性
2015年に発表された研究(Ibrahimiら、Neurology誌)では、月経関連片頭痛(MRM)の女性と健常な女性を比較し、ホルモンと神経の反応性の違いが調べられました。
この研究では、皮膚に刺激を加えてCGRPによる血管の反応(血流の変化)を測定し、次のようなことがわかりました。
- 健常な女性では月経第1~2日目にCGRPの血管拡張反応が大きくなる傾向がある
- 一方、MRM患者ではその反応の変化が乏しく、月経周期における血管反応のリズム(周期性)が失われていた
- MRM患者は、月経前(黄体期)において血中エストロゲン(エストラジオール)濃度が健常女性よりも有意に低いことも確認された
これにより、ホルモンの変化に対する神経の反応性そのものが乱れている、あるいはエストロゲンの減少に対する感受性が過剰になっている可能性があると考えられています。
治療と予防には「ホルモンの波」を意識することが重要です
月経に関連する片頭痛には、通常の鎮痛薬に加えて、次のような周期を意識したアプローチが有効とされています。
- 頭痛の記録をつけ、月経との関連を可視化する
- ストレス管理や規則正しい生活でホルモンバランスを整える
- 月経前後の不調には、漢方薬(当帰芍薬散、加味逍遙散など)が処方されることも
症状に合わせて医師が処方した薬を活用しながら、規則正しい睡眠やバランスの取れた食事、ストレス管理など、生活習慣の見直しによってホルモンの安定を図ることも大切です。
※特に純粋型(月経時のみ発症するタイプ)の方は、ホルモン補充療法によって効果が得られやすいとも言われています。
「生理のたびに頭が痛い」は我慢せず、まずは当クリニックに相談を
「生理のたびに片頭痛がひどくなる」「毎月寝込んでしまう」といった症状がある場合は、体質やストレスだけでなく、ホルモンの影響を疑ってみることが大切です。
日頃から頭痛と月経の関係を記録し、専門医による診断と治療を受けることで、適切な対策が見つかる可能性があります。
えびな脳神経クリニックでは、月経関連片頭痛を含む、女性の片頭痛に対する丁寧な診断と治療をおこなっています。
市販薬での対応が難しくなってきた方、発作が生活に支障をきたしている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
参考情報
本記事は、以下の文献・資料を参考に作成しています。
一般社団法人日本頭痛学会「国際頭痛分類 第3版(ICHD-3)」
https://www.jhsnet.net/pdf/ICHD3_up/171_02057_2_17.pdf
日本頭痛学会トピックス「月経関連片頭痛」