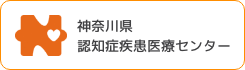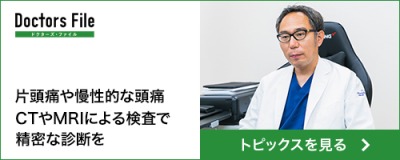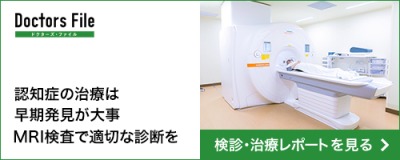2025/07/23
この記事を書いた人

医療法人社団NALU
理事長 尾﨑 聡
日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
日本脳神経血管内治療学会 脳血管内治療専門医
日本脳卒中学会 脳卒中専門医
認知症サポート医
医学博士

脳の病気は突然発症し、患者さんやご家族の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。
海老名市にあるえびな脳神経クリニックでは、病気を「点」ではなく「線」で支える医療を実現し、脳の疾患でお困りの方をゼロにすることを目指し、日々診療にあたっています。
本ブログでは、院長の岩田 智則と理事長の尾崎 聡が、脳の健康を守るための情報をわかりやすくお伝えしてまいります。
前回は「頭痛の種類と対処法」についてご紹介しましたが、今回はその中でも多くの方が悩まされている「片頭痛」に焦点を当て、その治療法についてくわしく解説します。
薬物療法や生活習慣の改善に加え、日本頭痛学会が推奨する「頭痛体操」についてもご紹介しますので、片頭痛の予防や改善を目指す方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
こんな片頭痛のお悩み、ありませんか?
- 月に何度もズキズキとした頭痛に悩まされている
- 痛み止めを飲んでも効かないことがある
- 光や音がつらくて、外に出るのが億劫になる
- 仕事や家事に集中できず、日常生活に支障をきたしている
- 天気やホルモンの変化で頭痛が起こる気がする
片頭痛は、ただの頭痛とは異なり、脳の神経や血管の異常が関係している慢性疾患です。
正しい治療を受けることで、痛みの頻度や強さを抑えることが可能です。
片頭痛の治療は「発作時」と「予防」の2本柱
片頭痛の治療は大きく2つに分けられます。
ひとつは頭痛が起きたときの「発作時治療」、もうひとつは日常的に片頭痛を繰り返す方への「予防治療」です。
発作時治療(頭痛が出たときの対処)
片頭痛の発作が起きたときには、痛みを素早く抑えることが大切です。
市販の鎮痛薬(ロキソニン・イブなど)
痛み始めにすぐ服用することで効果が得られやすくなります。
ただし、頻繁に服用すると「薬物乱用頭痛」につながるため注意が必要です。
トリプタン製剤(医師による処方薬)
片頭痛専用の薬で、頭の血管の拡張を抑える作用があります。
発作時の痛みだけでなく、吐き気や光過敏などの随伴症状にも効果が期待できます。
制吐剤
吐き気が強い場合や、薬の吸収を妨げる症状があるときに併用されます。
予防治療(発作を起こさないための体質改善)
月に2回以上の片頭痛発作がある場合、あるいは生活に支障をきたす頭痛が月に3日以上ある場合は、予防的な治療が推奨されます。
内服による予防薬
β遮断薬、抗てんかん薬、カルシウム拮抗薬、抗うつ薬など、患者さんの体質や他の疾患に応じて使い分けます。
CGRP関連薬(注射薬)
片頭痛の新しい治療法として注目されている薬です。
頭痛の発症に関わる神経伝達物質「CGRP」をブロックすることで、発作の回数や強さを大幅に抑える効果が期待されます。月に1回の皮下注射で、副作用も比較的少ないのが特長です。
生活習慣の見直しも治療の一環
薬だけでなく、日々の生活の中にも片頭痛を予防するヒントがあります。
睡眠リズムを整える
寝すぎ・寝不足を避け、毎日同じ時間に寝起きすることが大切です。
空腹を避ける
低血糖が片頭痛の誘因になることがあります。
朝食を抜かないようにしましょう。
ストレス対策を意識する
軽い運動や深呼吸、好きな音楽を聴くなど、自分なりのリラックス方法を見つけましょう。
刺激物の摂取に注意
チョコレート、赤ワイン、チーズ、カフェインなどが誘因になることもあるため、体調と合わせて控えめに。
気圧の変化に備える
天候アプリや気圧予報を活用し、頭痛が起きやすい日には事前に予防薬を服用することも一つの手段です。
自宅でできる「頭痛体操」も予防に有効です
片頭痛や緊張型頭痛でお悩みの方に、日本頭痛学会が監修した「頭痛体操」が注目されています。
これは首や肩の筋肉をやさしく動かすストレッチ体操で、片頭痛の予防や緊張型頭痛の軽減に効果があるとされています。
参考:“頭痛体操”.一般社団法人頭痛学会.https://www.jhsnet.net/pdf/zutu_taisou.pdf .(参照2025.03.10)
どうして頭痛体操が効くの?
片頭痛の発作が頻繁になると、脳内の痛みの伝達経路が首の後ろにまで影響を及ぼし、筋肉がこわばって「痛みのしこり」を作ってしまうことがあります。
そこで、頭痛体操を行うことで首の後ろ(後頚筋)の筋肉をほぐし、脳の痛み調節系に良い刺激を送ることができるのです。
また、緊張型頭痛は「ストレス頭痛」とも呼ばれ、肩や首の筋肉の緊張が原因になることが多くあります。
頭痛体操を日常的に取り入れることで、首から肩にかかるストレスをやわらげ、筋緊張による頭痛を防ぐことができます。
頭痛体操のやり方
後頚筋伸ばす体操(1日2分)
- 頭を動かさず、正面を向いたまま両肩を大きく回します
- 頚骨首の骨)を軸にして、肩と腕を左右交互に回します
- 無理のない範囲でリズミカルに動かしましょう
ポイント
- 頭は動かさないようにしましょう
- 体の軸を意識してみましょう
- 腕の力は抜いておこないましょう
この体操は、頭を支える筋肉(インナーマッスル)をやさしくストレッチし、筋肉のこりや疲れをとることで頭痛の軽減につながります。
僧帽筋を伸ばす体操(6回程度)
- 椅子に座ったままでできます
- ひじを軽く曲げて、肩を前後に回します
- 前に回すときは「リュックを背負うように」、後ろに回すときは「上着を脱ぐように」イメージしましょう
- 慣れてきたら、左右の肩を交互に前へ突き出すように体を回します
ポイント
- 肩の力を抜いて、無理なくおこなうようにしましょう
- 大きく動かして、筋肉に心地よい刺激を与えるようにしましょう
頭痛体操での注意ポイント
このような場合には頭痛体操をおこなわないでください。
また、ろれつが回らない、視界が二重に見える、めまい・けいれんなどがある場合は、命に関わる重篤な病気の可能性もあります。
いつもと違う頭痛を感じたときは、すぐに医師にご相談ください。
- 片頭痛の発作中
- 激しい頭痛があるとき
- 発熱を伴う頭痛があるとき
えびな脳神経クリニックでの片頭痛治療
えびな脳神経クリニックでは、片頭痛に対する的確な診断と個別に合わせた治療をおこなっています。
- 生活背景や頭痛の頻度を細かく聞き取る丁寧な問診
- 必要に応じてMRI検査を行い、脳の異常をチェック
- 症状やライフスタイルに合わせた薬の選択と調整
- 最新の治療法(CGRP製剤)にも対応しています
片頭痛は、適切な治療と生活習慣の見直しによってコントロールが可能な病気です。
「体質だから仕方ない」とあきらめず、早めに専門医の診察を受けることが大切です。
えびな脳神経クリニックでは、お一人おひとりの症状に合わせた最適な治療をご提案し、頭痛のない日常をサポートしています。
市販薬では対応しきれない方や、月に何度も寝込むようなつらい症状にお悩みの方も、ぜひ一度ご相談ください。
最新の治療法も含めて、しっかりと対応させていただきます。