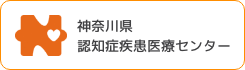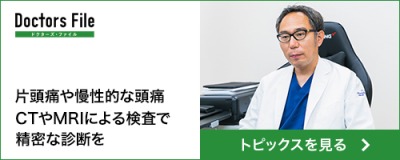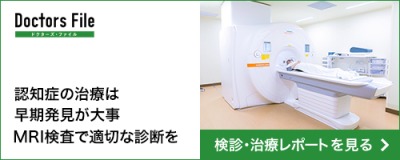2025/08/30
この記事を書いた人

えびな脳神経クリニック
院長 岩田智則
日本脳卒中学会(評議員)
日本血管内治療学会(評議員)
日本脳循環代謝学会(評議員)
米国心臓協会国際フェロー(Fellow of AHA・脳卒中部門)
日本神経学会専門医/指導医
日本内科学会総合内科専門医/指導医
日本脳卒中学会専門医指導医
日本認知症学会専門医指導医
厚生労働省認定外国人医師臨床修練指導医

脳の病気は突然発症し、患者さんやご家族の人生に大きな影響を及ぼすことがあります。
海老名市にあるえびな脳神経クリニックでは、病気を「点」ではなく「線」で支える医療を実現し、脳の疾患でお困りの方をゼロにすることを目指し、日々診療にあたっています。
本ブログでは、院長の岩田 智則が、脳の健康を守るための情報をわかりやすくお伝えしてまいります。
今回は「認知症予防と食事・生活習慣」についてご紹介します。認知症は高齢者だけの問題ではなく、誰にとっても身近な課題。
毎日の食事と生活の積み重ねが、将来の脳の健康に大きく関わってきます。
目次
脳を守るために、今できること
認知症は、加齢とともにリスクが高まる疾患の一つですが、その発症や進行には生活習慣の影響も大きいことがわかってきました。
中でも食事は、日々の積み重ねで脳を守る力となる重要なファクターです。
今回は、認知症予防に効果が期待される栄養素や食品、そして日常で気をつけたい食生活のポイントについてご紹介します。
認知症とは?
「認知症」とは、脳の病気や障害により記憶力・判断力・理解力などの認知機能が徐々に低下し、日常生活に支障が出る状態を指します。
認知症についてもっと詳しく知りたい方はこちら
主な認知症の原因となる疾患
| アルツハイマー型認知症 | 脳にアミロイドβたんぱく質が蓄積し、神経細胞が障害されていく |
| 血管性認知症 | 脳梗塞や脳出血など、脳血管の障害によって発症 |
| レビー小体型認知症 | 幻視や認知の揺らぎ、パーキンソン症状を伴う |
| 前頭側頭型認知症 | 人格や行動の変化、言語障害などが目立つ |
いずれのタイプも完治は難しいとされますが、早期の予防や対策により進行を遅らせ、患者・家族の生活の質を低下させないことを目標として対応します。
認知症予防のカギは、「脳の老化を防ぐこと」
脳の老化を進める要因の多くは、生活習慣病と密接に関連しています。
認知症は「高齢になると自然に起こるもの」ではなく、生活の見直しで発症リスクを下げることが期待できるのです。
認知症を予防するために大切なことは、栄養素の取り方と食習慣の質です。
認知症予防に効果的な食習慣
バランスの取れた食事を基本に
五大栄養素(たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラル)をバランスよく摂ることが基本です。
| オメガ3脂肪酸(DHA・EPA) | 青魚に豊富脳神経の構成成分で、神経伝達の安定にも関与 |
| ビタミンC・E・A、葉酸 | 抗酸化作用により神経細胞を守る |
| ポリフェノール・ファイトケミカル | 植物性食品に多く、老化の進行を防ぐ |
カロリーと肥満をコントロール
摂取カロリーが多すぎると肥満に直結し、アルツハイマー病や血管性認知症のリスクを高めます。
特に中年期の肥満が、後年の認知症リスクだけでなく他の疾患の発症にも危険因子となりますので注意しましょう。
大切なポイント
- 腹八分目を意識する
- 加工食品やジャンクフードの頻度を下げる
- 炭水化物は精製されていないもの(玄米・全粒粉)を選ぶ
塩分は控えめに
高血圧は脳血管障害の最大のリスク因子となります。
塩分の摂りすぎは血圧を上げ、脳梗塞や微小出血の原因となり、結果的に認知症につながります。
実践のコツ
- 和食の出汁や香辛料で減塩
- 漬物・干物・味噌汁などの塩分を見直す
- カリウムを含む野菜や海藻を意識的に摂取しましょう
糖分・間食はほどほどに
糖尿病や耐糖能異常も認知症リスクを上げます。
特に血糖値の乱高下は脳に悪影響を及ぼします。
控えたい食品
- 甘いお菓子や清涼飲料水
- 白いパン・白米などの精製糖質
- スナック菓子・菓子パン
認知症予防におすすめの食品
| 食材・成分 | 働き・特徴 |
| 青魚(さんま・さば等) | DHA・EPAが豊富記憶・判断力の維持に効果が期待 |
| 緑黄色野菜・豆類・果実類 | 葉酸が豊富ホモシステインを抑え血管と脳を保護 |
| カレー(クルクミン) | 脳のアミロイドβの分解を促す可能性あり |
| コーヒー(クロロゲン酸) | 抗酸化作用で老化防止 |
| 緑茶(テアニン) | 神経細胞の保護とリラックス効果 |
| 赤ワイン(ポリフェノール) | 適量で抗酸化・血流改善効果が期待 |
「調理」は最高の脳トレーニング!認知症予防にも効果的
「自分で料理をする」ことは、認知機能の維持に非常に有効です。
- 計画性(何を作るか)
- 手順(段取り)
- 運動(調理中の立ち作業)
料理の一連の流れは、単純作業の繰り返しではありません。
実は、認知症予防に非常に効果的な「脳の総合エクササイズ」なのです。
前頭葉を活性化する“献立から盛り付けまで”の流れ
- 献立を考える(何を作る? 栄養は足りている?)
- 食材を買いそろえる(冷蔵庫の中身を把握する)
- 材料を切る・加熱する(タイミングや順序を判断)
- 盛り付ける(彩りや配置を考慮)
これらの過程は、すべて脳の司令塔「前頭葉」が関与しています。
前頭葉は、記憶・計画・判断・注意力・感情の制御などをつかさどる重要な部位であり、認知症初期から機能低下が見られる場所でもあります。
調理を通じて前頭葉を継続的に刺激することが、脳の萎縮を防ぐ一助になると考えられています。
手指の運動が「感覚野」「運動野」を活性化
料理中は、包丁で切る・野菜を洗う・火加減を調整するなど、繊細な手作業が多数あります。
これらの動きは、脳の「運動野」や「感覚野」にしっかりと刺激を与えます。
| 巧緻性(こうちせい) | 協調性 | 集中力 |
| 手や指先を器用に動かす力 | 目と手、感覚と動作の連携力 | 焦げつかせない・分量を守るなどの注意深さ |
これらはすべて、加齢とともに衰えやすい認知・運動機能ですが、料理をすることで自然に維持・鍛えることができます。
複数の脳領域を“同時に”使うマルチタスク
料理は、考えながら手を動かし、味見をして、時間を調整するというマルチタスク作業です。
このような複数の脳部位が同時に働きます
- 前頭前野(計画・判断)
- 頭頂葉(空間認識・道具操作)
- 側頭葉(聴覚・記憶)
- 小脳(バランス・手先の微細な動き)
“脳全体を活性化させる日常動作”と言っても過言ではありません。
お一人暮らしでもできる、小さな料理習慣
- 朝食に味噌汁だけでも自分で作ってみる
- 昼食用に野菜を刻んでサラダを作る
- カレーなど工程の多い料理に挑戦してみる
こうした小さな積み重ねが、脳の健康を支えます。
市販のお惣菜や外食が多い方こそ、「自炊の再開」が認知症予防の第一歩となります。
毎日の積み重ねが、脳を守る力になります
認知症は誰にでも起こりうる身近な病気ですが、日々の食生活や生活習慣の見直しによって予防や進行の抑制に期待が持てる病気です。
特に、青魚や野菜、果物、発酵食品、抗酸化成分を意識した食事、糖分や塩分の過剰摂取の回避が、脳の健康を守るカギになります。
また、自分で調理する習慣は、献立の作成から盛り付けに至る一連の動作が脳を多面的に刺激し、認知機能の維持に貢献します。
こうした日々の取り組みとあわせて、気になる症状があるときは専門医への相談も大切です。
えびな脳神経クリニックの取り組み
当クリニックでは、神奈川県から認知症疾患医療センター(認定型)に指定され、海老名市の「認知症初期集中支援チーム」の事業も受託し、次のような支援を通じて、地域の皆さまの脳の健康をお守りしております。
- 認知症の専門的な診断・治療
- 地域の医療機関や介護施設との連携支援
- ご本人やご家族への相談対応・ケアの指導
- 必要時には検査のご案内も迅速に対応
気になる症状がある方、ご家族でご心配な方は、お気軽に当クリニックまでご相談ください。